こんにちは、あるいはこんばんは、家事「したくない」諸君。
『ない家事研究所』の Tanjism(タンジズム)だ。
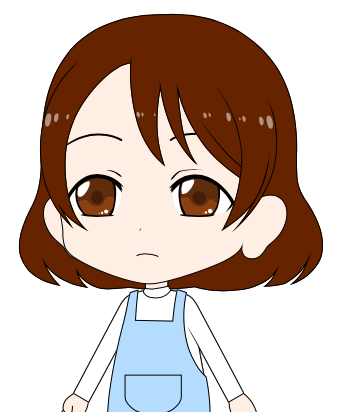
毎日の家事が辛いんです。
と言う諸君、本当に今までよく頑張ってきたと思う。
一人孤独に頑張った日もあっただろう。
ただでさえ仕事や育児・介護が大変な上に、さらに家事までこなしていくのは、肉体的にも精神的にも大きな負担になっていたことと思う。

さぞかし辛かったことだろう
私タンジズムも諸君の「家事が辛い」と言う気持ちには共感することが出来る。
さてここで、
私は諸君に「でも、みんな頑張っていることだから、君も頑張ろう!」と言うつもりは全く無い。
それでは「名前詐欺」になってしまう。
はじめましての諸君は、目に留まっていないかもしれないが、実はこのサイト名は『ない家事研究所』と言うのだ。
この『ない』には「したくない」 「しない」と言う意味が込められている。
自分が「したくない」ことに、人生を使うのはもったいない!
「したくない」ことは、「しない」方がいい!
だから「したい」ことが自由にできる、最高の人生を送ろう!
そのような考えのもと、情報発信基地として、この『ない家事研究所』を立ち上げた。
だから
「毎日、家事が辛い」と言う諸君には、私タンジズムは「やめていいよ」と伝えたい。
いや、むしろ「やめるべきだ!」と断言した方がいいかもしれない。
「辛い」という気持ちは、あなたの体からの危険信号で、今すぐにでもやめないと手遅れになる恐れがあるからだ。
さらに言うと、
そんなに「したくない」と思うような家事はやめて当然である。
やめたからといって、特別後ろめたい気持ちを持つ必要も無い。
今回は「毎日、家事が辛い」と嘆く諸君に向けて、私タンジズムが「やめるべきだ!」と断言する理由を説明する。
この話を聞いた諸君が、辛い家事から解放されてくれることを祈っている。
「辛い」は体からの危険信号

まず重大なことをお伝えしておく。
「辛い」を「辛い」まま放っておくことは、最悪の場合、生命の危機につながる恐れがある。
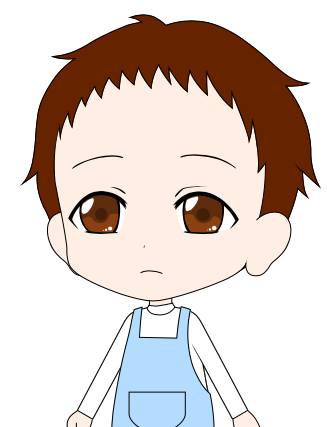
また、タンジズムが話を盛っているな
と言う諸君。
今回の話は冗談では済まされないので、真剣に聞いて頂きたい。
諸君は「過労死」という言葉を知っていると思う。
しかし、
諸君の多くは「自分には関係無い」と思っていないだろうか?
これは「正常性バイアス」と呼ばれるもので、異常事態に対して「自分がなるわけない」という先入観で、心を自動的に落ち着かせる心の仕組みのことだ。
正常性バイアスの「バイアス」は偏見、先入観といった意味です。つまり正常性バイアスとは、多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保とうとする働きのことです。この働きは、人間が日々の生活を送るなかで生じるさまざまな変化や新しい出来事に、心が過剰に反応し、疲弊しないために必要な働きです。
出典:総合南東北病院 新しい医療用語 正常性バイアス より(https://www.minamitohoku.or.jp/up/news/newword/normalcybias.htm)

正常性バイアスは、
心を落ち着かせるという「良い面」もある一方で、
自然災害などの「想定外」なことに直面した際に、リスクを過小評価してしまうという「悪い面」もあるんだぞ。
日本において「過労死」は、現在進行形で社会問題となっているので、ぜひこの機会に諸君も「自分ごと」として捉えて頂きたいと思う。
過労死
過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡に至ることを意味します。また 過労自殺は過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」など精神疾患を発症し、自殺してしまうことを意味します。
出典:過労死110番全国ネットワーク(https://karoshi.jp/learning/whatiskaroshi.html)
過労死は、特に日本において重大な社会問題である。
それもそのはず、
世界で初めて過労死が特定されたのが日本であり、現在は「Karoshi」と国際語となるほど世界的にも認識されているのだ。
なんとも不名誉ではあるが、この日本の社会の現状は一旦受け止めなければならない。
ところで、
過労死の原因として「仕事による過労・ストレス」が挙げられている。
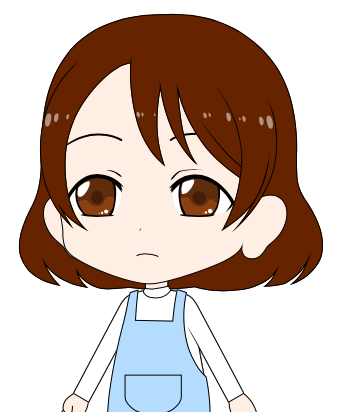
つまり家事による過労は無いってこと?
と、先走らないでほしい。
家事も立派な仕事だ。
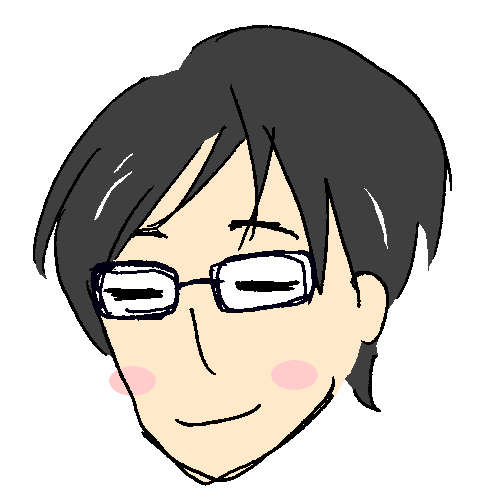
仮に「家事は仕事ではない!」と言ってくる者がいても、わざわざ諸君が相手する必要は無いぞ。
この『ない家事研究所』へ連れてきてもらったらいい。

そうだ、タンジズムの言う通り。
それでも話が通じない者だった場合は、潔くその人とは関係を断ち切る、もしくは相手にしないことが一番だ。
なぜなら、その人はあなたの人生を幸せにできないからだ。
つまり、
家事による過労やストレスも過労死の原因の一つと言えるので、「毎日、家事が辛い」状況というのは十分に危険な状態であると言えるだろう。
このままだと、過労で倒れてしまうかも!?

過労で倒れるというのは、どういう状態か考えたことがあるだろうか?
脳・心臓疾患の労災認定基準では、対象となる疾病(脳出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤)の発症が、労災と認められるための基準が示されています。
出典:過労死110番全国ネットワーク(https://karoshi.jp/learning/whatiskaroshi.html)
ここで挙げられた脳出血や脳梗塞、心筋梗塞や狭心症などの病気は、一般的にはタバコやアルコール、食生活や運動不足など日々の生活習慣が原因と言われている。
このような「いかにも不健康そうな生活」が習慣化し、さらに加齢や遺伝的な要因などが加わり、積み重なっていくうちに徐々に悪化し発症にいたる。
これは特別「労働者」に限定せず、世間一般的なすべての人が起こりうる病気である。
ところが、
「過労で倒れる」状態というのは、生活習慣などで「徐々に悪化」するという部分をすっ飛ばして、「過度な労働」によって急激に症状が悪化し上記のような脳・心臓疾患で突然倒れてしまう状態を指す。
これは、業務を遂行することによって生体機能に引き起こされる多様なストレス反応(※)について、恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、ストレス反応は持続し、かつ、過大となり、ついには回復し難いものとなり、この疲労の蓄積によって、生体機能が低下し、血管病変等が増悪することがあると考えられるからであり、(中略)現時点での医学的知見に照らしても妥当と判断する。
出典:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書より(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832043.pdf)
(※)ストレス反応とは、職務不満足や抑うつなどの心理的な反応、血圧上昇、心拍数の増加、不眠、疲労感などの生理的な反応、疾病休業、事故などの行動面での反応などをいう
例えば、
仕事の繁忙期で睡眠時間が数時間しか取れない生活を1週間過ごしたとしても、その後しっかりと休養を取ることができれば、疲労の回復は十分可能だろう。
しかし、
そのような長時間労働やストレスなどが長期間継続してしまい疲労が蓄積し続けた結果、急激に脳・心臓疾患を発症してしまうのである。
特に、
「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の中では、「睡眠不足」と「疲労の蓄積」との強い関係性を指摘している。
そのなかでも、疲労の蓄積をもたらす要因として睡眠不足は深く関わっているといえ、本検討会は、現時点の疫学調査の結果を踏まえても、引き続き、1日5~6時間程度の睡眠が確保できない状態が継続していた場合には、そのような短時間睡眠となる長時間労働(業務)と発症との関連性が強いと評価できるものと判断する。
出典:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書より(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832043.pdf)
ここでは、
睡眠時間が1日5~6時間確保出来ない状態が継続すると、脳・心臓疾患の発症リスクが高まることを指摘している。
この「1日5~6時間の睡眠時間」というのは、また後ほど登場するので、覚えておいてほしい。
「働き方改革」
1日の睡眠時間についてはまた後から登場するとして、ここでは少し話題を変えるぞ。
最近「働き方改革」という言葉をよく耳にすると思う。
これは2019年から段階的に(一部業種は2024年4月までに、一部特例あり)、日本で働く人を対象とした時間外労働の上限規制が導入されたことに伴うものである。
まず忘れてはならないのが、労働基準法の大原則として下記の2点があることだ。
・労働時間は1日8時間かつ週40時間以内
・休日は毎週1回以上
すなわち、
基本的に時間外労働=残業は、しないに越したことはない。
しかし、
繁忙期など業務上やむを得ない状況など臨時的な事情がある場合には、労使間で協定を結んだ上での長時間労働が認められていた。
ところが以前までは、
罰則の強制力が無かったり、上限無く時間外労働を行わせることが可能だったり、いわゆるブラック企業が労働者を「働かせ放題」だったわけである。
結果、
過労死を含めて健康への悪影響、仕事・家庭の両立の困難化、少子化の原因ともなっていた。
そのような状況下で、長時間労働を是正するために時間外労働の改定が行われたのだ。
新たなルールの中で、「80時間」や「100時間」など様々な時間の規定があるのだが、正直言って割とややこしい。
しかし、このあたりの時間が先ほどの睡眠時間との関係性を説明する「キー」となってくるので、諸君にもよく理解しておいてほしい内容だ。
改めて、時間外労働の上限規制の改正のポイントを抑えておく。
★時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定された★
◯法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間かつ年間360時間以内
※臨時的な特別な事情を除く
◯臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合は、下記のルール内であればOK
・時間外労働が年間720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日の合計について、連続2ヶ月〜連続6ヶ月平均がすべて1月あたり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは、年6ヶ月まで
◯上記に違反した場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 時間外労働の上限規制わかりやすい解説より参照(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf)
上記の新ルールをもとに、いくつかのケースに分けて時間外労働時間の例をまとめてみた。
◎1ヶ月20日間働いた場合の1日の平均残業時間
★時間外労働が月30時間
→1時間30分
★時間外労働が月45時間
→2時間15分
★時間外労働が月60時間
→3時間
★時間外労働が月80時間
→4時間
★時間外労働が月100時間
→5時間
◎年間時間外労働時間の上限ごとの月の平均残業時間の例
★時間外労働が年間360時間
→月30時間
★時間外労働が年間720時間
→6ヶ月間が月平均80時間と、残りの6ヶ月間は月平均40時間
時間外労働が月80時間というのは、例えば9時〜18時(休憩1時間含む)まで通常業務を行った上で、毎日22時まで残業を行なっているということだ。
これが時間外労働が月100時間となると、毎日23時までの残業ということである。
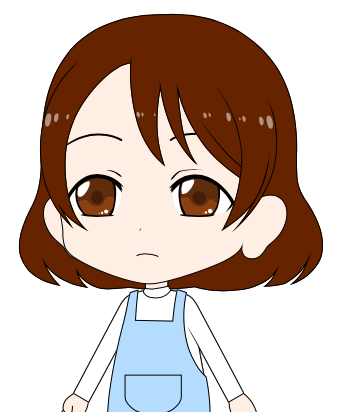
そんなのブラック企業ではないか?
しかし、
「連続2〜6ヶ月間の平均がすべて80時間以内」というルール上、連続した月で100時間の残業は違法だが、単月に限っては毎日23時までの残業は合法なのである。
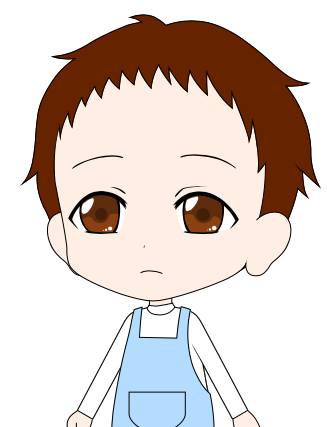
そんな遅い時間まで働いていたら、寝る時間が無いのでは?
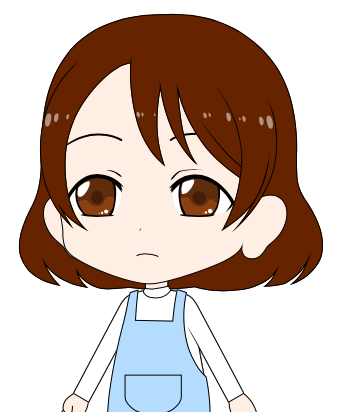
何を根拠に、80時間とか100時間とか決めたの?
と思った諸君は鋭いぞ!
先ほど一旦寝かせておいた(睡眠だけに)「睡眠時間」が、ここで関係してくるのだ!
労働時間と睡眠時間の関係性
日本の有業者の平均的な生活時間を調査した平成 28 年の社会生活基本 調査(中略)によると、15 歳以上の有業者の平日の睡眠時間は 7.2 時間、仕事時間は 8.1 時間、食事、身の回りの用事、通勤等の生活に必要な時間(食事等の時間)は 5.3 時間となっている。
出典:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書より(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832043.pdf)
ちなみに、
上記のデータで24時間の残り3.4時間については、趣味・娯楽、休養・くつろぎ等の余暇の時間となっている。
「時間外労働」となった場合、生活時間の中から真っ先にに削られるのが「くつろぎ等の余暇の時間」だろう。
この「くつろぎ等の時間」が3.4時間。
それでも足りない場合、さらに「睡眠時間」が削られる対象になってしまうのだ。
ただでさえ「睡眠時間」7.2時間は、世界的に見ても少ない。
経済協力開発機構(OECD)の生活時間の国際比較データによると、比較した11カ国中、睡眠時間が一番短かったのは日本だった。
男女ともに、1位のアメリカよりも70分以上も短いという結果だった。
(アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、韓国、日本の11ヵ国)
(出典:内閣府 男女共同参画局 生活時間の国際比較データより(https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/column/clm_01.html))
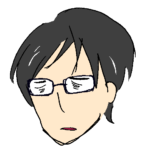
これ以上削ったらダメそうなことくらい、素人でも分かる。
しかし、
日本人はこの「睡眠時間」までも犠牲にしてしまうのだ。
これを前提とすると、現時点においても、1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外 労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね 80 時間(※1)を超える時間外労働が想定される。
また、1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間 8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが 1か月継続した状態は、おおむね 100 時間(※2)を超える時間外労働 が想定される。
(※1)24 時間から、生活を営む上で必要な睡眠(6時間)・食事等・仕 事(法定労働時間8時間及び法定休憩時間1時間)を引いた時間数に 1か月の平均勤務日数 21.7 日を乗じた概数。
(※2)前記の睡眠を5時間として同様に算出した概数。
出典:厚生労働省 脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会報告書より(https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832043.pdf)
睡眠時間が1日5〜6時間確保出来ない状態が継続すると、脳・心臓疾患の発症リスクが高まることを指摘されていたが、この「1日5〜6時間の睡眠時間」を確保するための根拠として、このように1ヶ月の時間外労働時間の説明がなされている。
要約すると、
①日本で働いている人の平均的な生活時間をもとに、
②1日5〜6時間の睡眠時間が確保出来ない状態を考えてみたところ、
③1日6時間確保出来ない場合、1日の労働時間8時間+残業4時間した場合に相当する。
④1日5時間確保出来ない場合、1日の労働時間8時間+残業5時間にた場合に相当する。
⑤その残業が1ヶ月継続したと考えると、残業の合計がそれぞれ80時間と100時間となる。
もちろん、
月に80時間や100時間という長期間にわたっての肉体労働やストレスにさらされ続けたりする「直接的」なリスクもあるだろう。
しかし一方で、
過度な肉体労働でもなくストレスも少なそうな場合であっても、長時間労働により睡眠時間が削られていき、結果として十分な睡眠時間を確保出来ない場合にも、健康にリスクがあると言えるだろう。
つまり、
時間外労働時間の月80時間や100時間が決められた根拠というのは、「直接的」というよりも、「間接的」に睡眠時間を確保するための時間だと言えそうだ。
家事労働と睡眠時間
ここまで「労働」の話ばかりを進めてしまい、「家事」のことを置いてけぼりにしてしまっていた。
しかし本題は「家事」のことである。
ここから先は「家事」を中心に話をしていく。
とはいえ、「家事」も「労働」の一部と考えることが出来るので、
「労働時間」=「仕事の労働時間」+「家事の労働時間」という考え方が出来るはずだ。
先ほど出した、日本の有業者の平均的な生活時間をおさらいしておく。
★15 歳以上の有業者の平日の平均的な生活時間
(1)睡眠時間: 7.2 時間
(2)仕事時間: 8.1 時間
(3)食事、身の回りの用事、通勤等の生活に必要な時間: 5.3 時間
(4)くつろぎ等の余暇の時間:3.4時間
ここで「家事の労働時間」は、上記の(3)に含まれるはずだ。
総務省統計局「令和3年社会生活基本調査の結果」から、(3)の詳細を見ていくことにする。

データの参照元が若干異なるのだが、
そこは誤差の範囲だと思って目をつぶって頂きたい。
★食事、身の回りの用事、通勤等の生活に必要な時間の詳細(テレワーク以外)
・食事:1.43時間
・身の回りの用事:1.32時間
・通勤・移動:1.27時間
・家事:1.16時間
(家事、介護・看護、育児、買い物含む)
・他:0.12時間
(出典:総務省統計局「令和3年社会生活基本調査の結果」生活時間及び生活行動に関する結果(令和4年8月31日)(https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/youyakua.pdf))
家事の時間が1.16時間(約70分)しか無いことに気づいただろうか?
家事の時間に対して、
諸君は「思っていたよりも少ない」と思ったかもしれないが、私も同意見だ。
特に共働き世帯で、まだ小さい子供がいるような家庭の場合は、家事と育児に追われて1.16時間以内には家事が収まらないのではないだろうか。
また一人暮らし世帯では、いくら「一人分」の家事とはいえ、家事の分担が出来ないので家事の負担が大きくなりがちだ。
仮に家事時間1.16時間を超えてしまったとしたら、それはすなわち、家事の「時間外労働」と言っていいと思う。
たとえば、
仕事で時間外労働を3時間行うとする。
これが1ヶ月継続すると月60時間くらいの時間外労働となり、「割と多い」とは言えるものの、健康的なリスクはあまり問題視されていない。
ところが、
この時に家事時間1.16時間を超えていたらどうだろう?
仮に家事の「時間外労働」が1時間あり、これが1ヶ月継続すると月20時間くらい。
「労働時間」=「仕事の労働時間」+「家事の労働時間」に当てはめると、
「労働時間」=60時間+20時間=80時間と、途端にレッドゾーンに入ってしまう。
家事の「時間外労働」1時間なんて、あっという間だ。
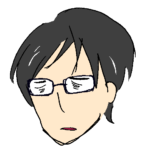
私も、キッチンに立っているだけで
1時間など3600秒で経ってしまう。
ここで問題なのが、家事の「時間外労働」を認知していないということだろう。
仕事の時間外労働の場合、タイムカードの打刻時間や給与明細で実感できる。
「今月は残業80時間もしてる!どうりで疲れているわけだ…」と。
しかし、
家事の時間外労働は、意識しない限り実感することが難しい。
「今月も忙しかったから疲れたな。あれ?今月は残業は40時間か…でも、疲れたなぁ…」と。
結局は仕事にしても家事にしても、頑張った代償として、くつろぎの時間や睡眠時間が犠牲になるのである。
くつろぎ・睡眠、いずれも体の疲れを回復させるための大切な時間である。
にも関わらず、
目先の「労働(家事労働が潜んでいる!)」を「しなければいけない」と思い込んでしまい、健康を害してしまうのだ。
そのような生活を続けているとどうなるか?
ある日突然倒れて、「過労死」してしまうのである。
心の病気について…

ここからは、
「毎日の家事が辛い。」が引き起こすであろう、心の病気について説明したい。
…と思っていたのだが、
恐らくもう諸君は、私の話に飽きてきた頃だと思う。
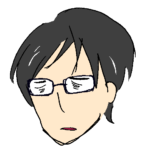
正直私も、
ここまで話すのに疲れたところだ…
ということで、一旦ブレイクタイムを挟むことを(一方的に)提案する。
また、改めて続きの記事を準備するので、それまで諸君は睡眠と休養を「しっかりと」取ってほしいと思う。
それでは、
いつもの言葉と共に、今回の記事を締めたいと思う。
他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる
諸君が「したくない」家事から解放されて、「したい」ことで人生を楽しんでもらうことを願って。


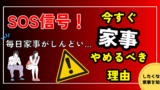
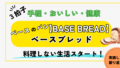
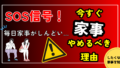
コメント